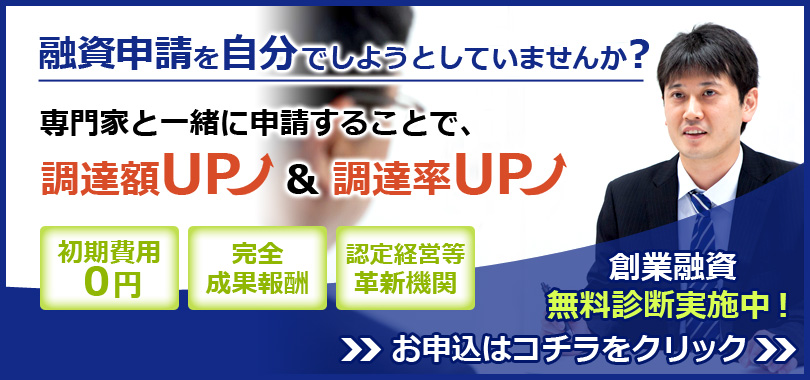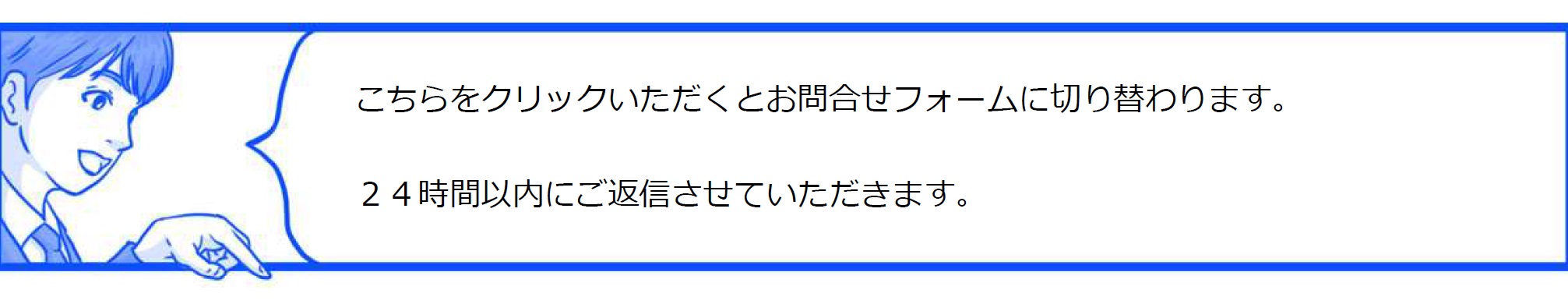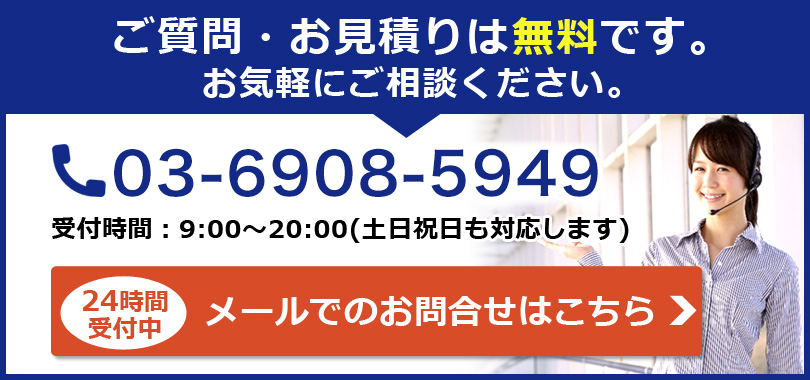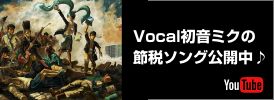税理士ブログ
相続税の節税策として適用を受けるべき「小規模宅地等の特例」
はじめに
こんにちは、新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士阿部です。
相続税の計算において、大きな節税効果をもたらす制度があります。
それが、「小規模宅地等の特例」です。
この制度、適用できるかどうかで相続税が数百万円単位で変わることも珍しくありません。
なのに…知らない人が多い。
制度の存在すら知らずに申告して、あとから「やっておけばよかった…」と後悔する方も。
この記事では、小規模宅地等の特例の基本的な内容と、注意すべきポイントをお伝えします。
相続税対策の参考に、ぜひ最後までご覧ください。
■ 小規模宅地等の特例とは?
ざっくり言えば、「被相続人(亡くなった方)の自宅などの土地について、相続人が条件を満たせば、土地の評価額を最大80%引き下げますよ」という制度です。
評価額が1億円の土地であれば、2,000万円に減額されて相続税が計算されるのです。
つまり、節税効果はとんでもなく大きいのです。
■ 対象となる宅地の種類
小規模宅地等の特例には、以下のような区分があります。
-
特定居住用宅地等(自宅):
最大330㎡まで、評価額を80%減額
⇒配偶者や同居の親族が対象 -
特定事業用宅地等(事業用地):
最大400㎡まで、評価額を80%減額
⇒家業を継ぐ場合など -
貸付事業用宅地等(賃貸用地):
最大200㎡まで、評価額を50%減額
⇒相続開始前3年以内に新たに貸した土地は対象外(節税目的排除)
宅地の種類によって、控除の内容や面積が異なるため、まずはどのタイプに該当するかを正確に判断することが大切です。
■ 適用要件はかなり細かい
制度のインパクトが大きい分、要件も細かく設定されています。
とくに注意すべきは、以下のようなポイントです。
● 同居していたかどうか
「同居してた」と言いつつ住民票だけ移していただけ…というケースでは適用されません。
● 配偶者の場合は無条件OK
配偶者が相続する場合は、無条件で適用されます。これは“税制上の最大級のやさしさ”とも言えます。
● 別居の親族は要件が厳しい
同居していなかった相続人(たとえば別の家に住んでいた子ども)が適用するには、被相続人に配偶者や同居の相続人がいないなど、条件のハードルが急にマラソンレベルに上がります。
■ 適用のための注意点
以下のような点も、申告時に意識しておかないと、特例が「使えない」「否認される」といった悲劇に見舞われます。
① 相続税の申告が必要
小規模宅地等の特例は、相続税の申告があって初めて適用される制度です。
相続税がかからないと思って申告しなかったら、この特例も適用できません。
② 申告期限まで宅地を保有しておく
相続税の申告期限(10ヶ月以内)までに土地を売却したり、名義を変更してしまうとアウトです。
③ 書類の提出が必要
単に「言えば適用される」わけではありません。
特例の適用には、別途明細書や資料の提出が必要。漏れると適用されません。
■ よくある質問(Q&A)
Q. 祖父名義の家を孫が相続できますか?
→条件によりますが、基本的には「法定相続人かつ要件を満たす親族」であることが前提です。孫の場合、かなり限定的。
Q. マンションの土地でも使えますか?
→マンションの敷地の持ち分でも、被相続人が住んでいた場合は対象になり得ます。
■ まとめ:使えるかどうかで人生が変わる制度
小規模宅地等の特例は、相続税対策において極めて大きい節税効果を持つ制度です。
一方で、要件や期限、実態確認など、「使えるかどうかの判断」が極めて重要です。
何より、「知らなかった」で適用を逃すことのないよう、事前の確認と計画的な対応が不可欠です。