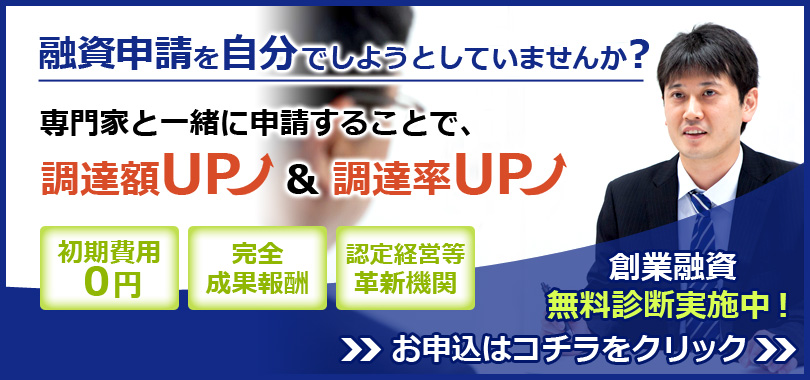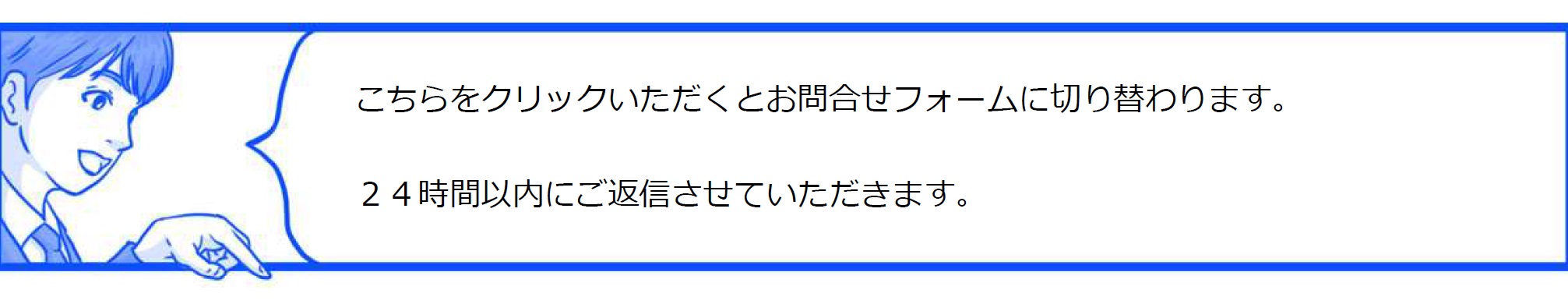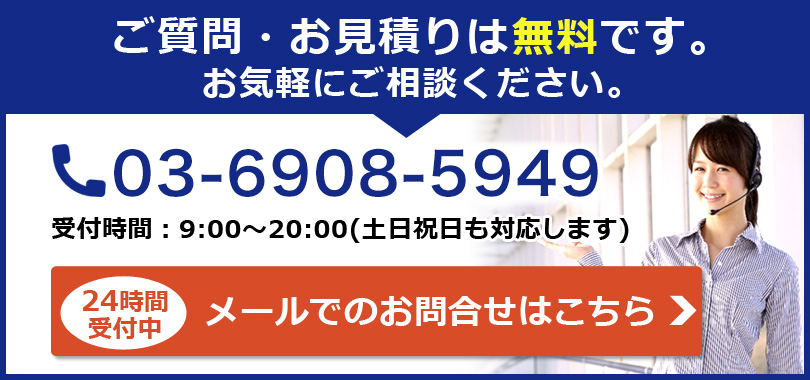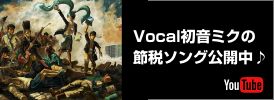税理士ブログ
「純資産?資本金・準備金・自己資本比率まで、まるっと解説します!」
こんにちは、新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士阿部です。
企業の決算書に出てくる「純資産」というワード、なんだか難しそうに見えますが、
実はとても大事な項目です。
今回はその中でも特に重要な、
-
資本金
-
資本準備金
-
利益準備金
-
自己資本比率
この4つに絞って、税務上の注意点や実務上のポイントをまじえながら解説していきます。
① 資本金について:会社の「出発資金」であり「信用力の顔」
資本金とは、会社が設立時に出資を受けたお金、
つまり「スタートダッシュのためのお財布」です。
会社法では1円からでもOKですが、取引先や金融機関はその額を意外と気にしています。
たとえば資本金1円の会社からの請求書を見たときに、
「この会社、本当にやる気あるのかな…?」と疑われる可能性も。
実際、ある社長が「1円起業で夢をかなえた」とSNSで語っていたら、
税務署よりも先にお取引先に疑われてしまいました…。
💡税務上の注意点:
-
資本金1,000万円未満なら消費税が2年間免除(免税事業者)
-
ただし、「期中増資」により資本金が1,000万円を超えた場合、その時点から課税事業者となる可能性あり
-
法人住民税の均等割にも影響あり(資本金額によって段階的に上昇)
👉 資本金は小さすぎても、大きすぎても戦略次第。慎重に設定しましょう。
② 資本準備金について:増資時の“裏方ヒーロー”
資本準備金は、増資をしたときなどに
「資本金として組み込まず、純資産の一部としてストックしておくお金」です。
たとえば株主から1,000万円を出資してもらったとき、
そのうち500万円を資本金、残りの500万円を資本準備金とする、という処理が可能です。
この仕組み、実は会社法で「最低半分は資本金にしてね」と決まっています。
“飲み放題で頼んだウーロン茶を全部飲まなくてもよい”という気持ちのゆとりに似ています(?)
💡税務上の注意点:
-
将来「利益準備金」や「剰余金」に組み替えることも可能
-
剰余金として取り崩す際は、株主総会決議などが必要
③ 利益準備金について:出た利益の“使い道に制限ありストック”
利益準備金とは、会社が利益を出した際に、
そのうちの一定額を“会社の中に積み立てておくお金”です。
「商法上の縛り」から生まれたこの制度は、会社の安定経営と債権者保護のためのものです。
利益が出たら全部配当したくなる経営者もいますが、そこにブレーキをかけるのがこの準備金です。
💡税務上の注意点:
-
減資や欠損填補時には取り崩しが可能(登記・議事録が必要)
-
配当とのバランスが重要:配当額の1/10以上を積み立てる義務あり(ただし制限あり)
👉 配当前にまず“会社の貯金箱”にコツコツ積み立てましょう。
④ 自己資本比率について
自己資本比率とは、総資産に占める純資産(=自己資本)の割合を示す指標です。
簡単に言うと、「借金に頼らず、どれだけ自前で経営しているか」を見る目安です。
この数字が高いほど、“筋肉質”な会社とされ、金融機関の評価もグンと上がります。
逆に自己資本比率が5%未満の会社は、片足だけでバランスボールに乗っているような状態です。
💡税務上の注意点:
-
自己資本比率そのものに直接税務影響はない
-
金融機関の融資審査や税務調査時の「健全性評価」に用いられる
-
毎年の利益積立(繰越利益剰余金)で徐々に改善を図れる
【おまけ】会計と税務の“純資産ズレ”にも要注意!
会計上の純資産と、税務上の資本金・剰余金の扱いにはズレがあることも忘れてはいけません。
たとえば、減資によって税務上の資本金等が圧縮されると、
外形標準課税や消費税の免税判定に影響します。
また、貸借対照表に表示されていない“みなし資本”が税務上評価されるケースも…。
【まとめ】“純資産”は見えにくいけど、見られてます。
資本金・準備金・自己資本比率……これらは取引先・銀行・投資家・税務署など、
あらゆる「外の目」から見られている数字です。
特に決算書を使って資金調達をする場面では、
これらの構成内容によって、評価が大きく変わります。