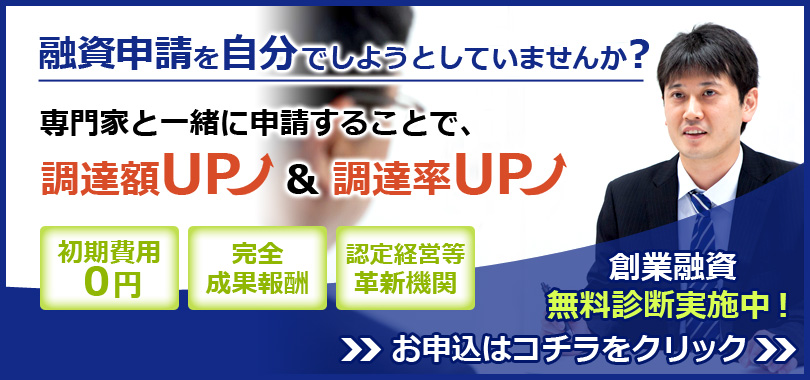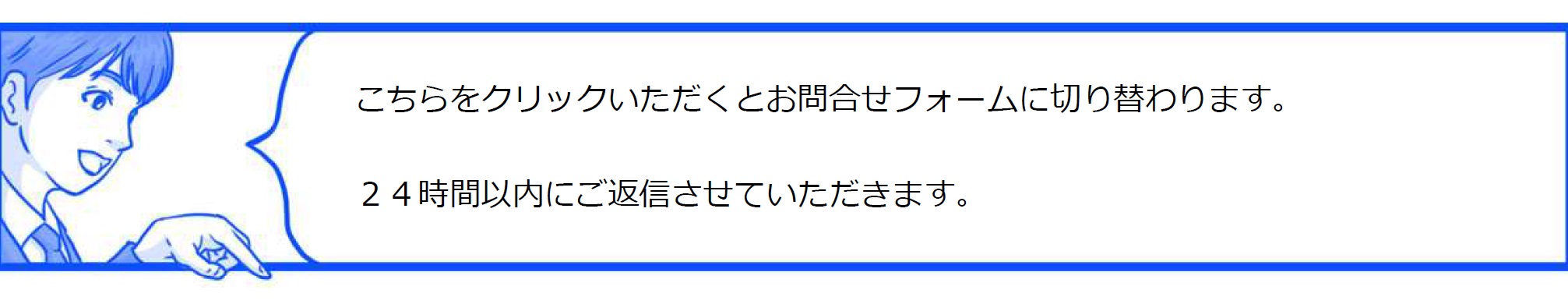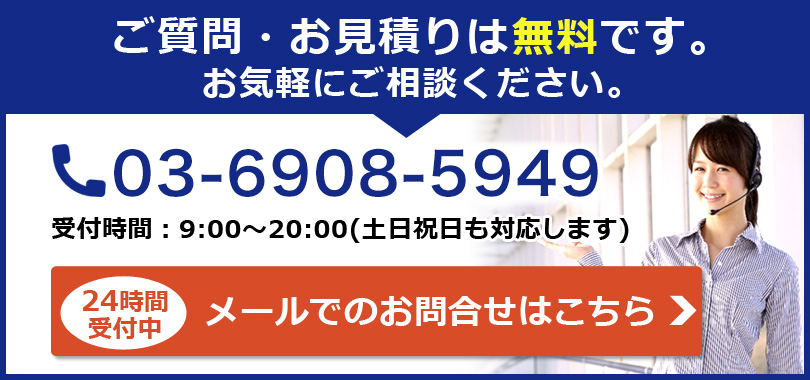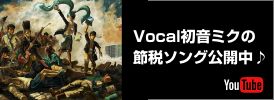税理士ブログ
音楽著作権と税金の話
こんにちは、新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士阿部です。
作曲家や作詞家、アーティストの方にとって、音楽著作権は“財産そのもの”ともいえる大切な権利です。
そしてその著作権から得られる収入には、当然ながら税金が関わってきます。
この記事では、音楽著作権に関わる方が押さえておきたい、税務上の基本事項と実務上の注意点を解説します。
■ 著作権収入=“所得”です。避けられません。
音楽著作権により得られる収入は、原則として「著作権使用料」=「雑所得」または「事業所得」に分類されます。
-
JASRACやNexToneなどの管理団体を通じて支払われる使用料
-
自ら販売した楽曲に関する収入
-
楽曲の二次利用(CM・ゲーム・映画)での使用料
-
YouTubeでのコンテンツIDによる収益
これらすべて、所得です。
■ 雑所得か?事業所得か?…ここが大きな分かれ目
音楽著作権収入は、ケースによって「雑所得」か「事業所得」のいずれかになります。
【雑所得】
→ 副業レベル、または継続性・独立性が乏しい場合
例:本業は別にあり、たまに楽曲提供する程度
【事業所得】
→ 専業または職業的に音楽を継続的に提供している場合
例:作曲家・アーティストとして年間複数本の提供実績がある
事業所得になると、青色申告が使え、65万円の特別控除や赤字の繰越などが可能になります。
継続的な売上と経費がなければ“事業”とは認められません。
■ 著作権譲渡による収入の扱い
著作権を「譲渡」した場合、これは資産の譲渡として扱われ、譲渡所得または事業所得になることもあります。
-
一時的に高額な収入が発生する場合
-
永続的な使用権を他者に移転した場合
このような場合は、雑所得と分けて考える必要があるため、申告区分を間違えるとリスクがあります。
また、譲渡の際に一括で大きな金額を受け取った場合、「その年だけ爆上がり」→「税率も爆上がり」という悲劇が起こりかねません。
■ 経費にできるもの・できないもの
著作権収入が事業所得と認められた場合、さまざまな経費を控除できます。代表例としては:
-
制作に使用した機材(パソコン、DAW、インターフェース等)
-
楽器、譜面、スタジオ代
-
関連書籍・音源購入費
-
セミナー・ワークショップの受講料
-
広告宣伝費(HP制作・SNSプロモーション等)
-
交通費、打ち合わせ費用(ただし、懇親会はほどほどに)
■ 所得の変動と税額の備え
著作権収入は、不定期かつ変動が激しいという特徴があります。
特にYouTubeや配信で“バズった”場合、急に数十万~数百万円の振込が来ることも。
しかし、翌年にはそのすべてに対して税金が課されます。
-
所得税
-
住民税
-
国民健康保険
-
場合によっては消費税(課税事業者の場合)
つまり、「バズったら、その後税金でもう一度バズる」という現象が起こりがちです。
対策としては:
-
年間の収入変動をざっくり予測
-
毎月一定額を“納税用預金口座”に積立てる
-
節税制度(青色申告、iDeCo、小規模共済)を活用
など、収入が安定しないからこそ、先を見越した設計が重要です。
■ まとめ|著作権は“文化”だけでなく“課税対象”でもある
音楽著作権は、創作者にとって大切な資産であり、活動の成果そのもの。
しかしその分、税務上の取り扱いは非常に繊細で、誤解や放置が後のトラブルにつながることも少なくありません。
-
所得区分(雑所得/事業所得/譲渡所得)を正しく判断
-
経費の判断に注意
-
収入の変動に合わせた納税準備
-
節税制度の積極的な活用
これらを押さえておくことで、音楽活動を安心して続けるための「財務の地盤」が整います。
当事務所では、音楽・芸術関係のクライアント様向けに、著作権収入やその税務処理に関するサポートを多数行っております。