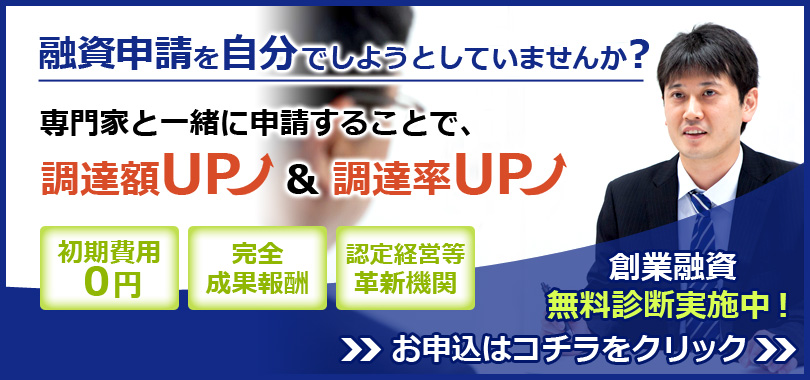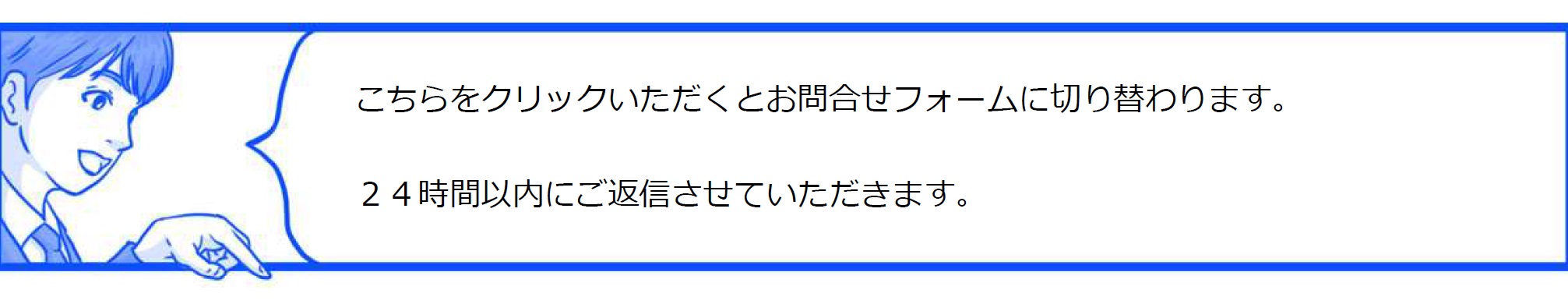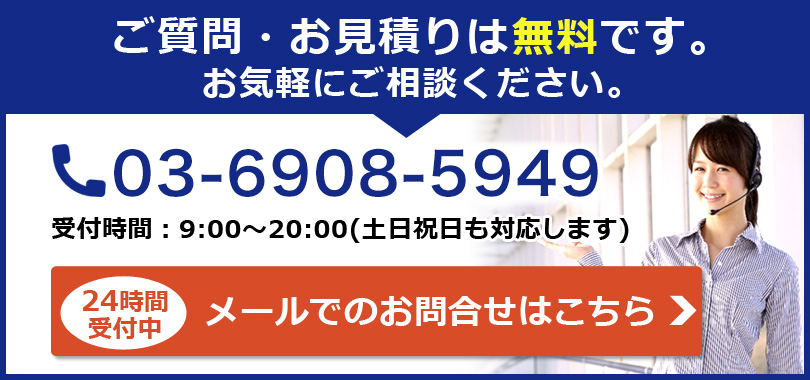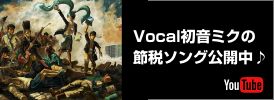税理士ブログ
相続税における「法定相続人」とは?|相続の主役たちと税務のリアル
こんにちは。税理士の阿部です。
相続税の計算において最も基本かつ重要なポイントのひとつが、「法定相続人は誰か?」という点です。
相続税の基礎控除額や税率の適用、生命保険の非課税枠など、多くの制度が「法定相続人の人数」に左右されるため、正確な理解が不可欠です。
この記事では、相続税法における法定相続人の考え方と、実務上よくある注意点を紹介します。
■ 法定相続人とは?民法と相続税法の接点
「法定相続人」とは、民法で定められた「遺産を受け取る権利のある人」のこと。
具体的には、次の優先順位で決まります。
【第1順位】子(直系卑属)
→ 子がすでに亡くなっている場合は孫へ代襲相続
【第2順位】父母などの直系尊属
→ 第1順位がいない場合のみ
【第3順位】兄弟姉妹
→ 第1・第2順位がいない場合
なお、配偶者は常に相続人となります。ここが重要。
■ 相続税の基礎控除は、法定相続人の人数で決まる
相続税には、課税対象となる金額を計算する前に「基礎控除」があります。
【基礎控除の計算式】
3,000万円+600万円 × 法定相続人の人数
例えば、配偶者+子2人の場合は、
→ 3,000万円+600万円×3人=4,800万円が非課税枠になります。
ここで重要なのが、「法定相続人の数を正しくカウントすること」。
-
養子は人数制限があります(被相続人に実子がいる場合は1人まで)
-
内縁の配偶者はカウントされません(法律上の婚姻が前提)
「籍入れてないけど、ずっと一緒にいたから実質夫婦」理論は、法律にはありません。
税務署は“心の距離”ではなく“戸籍の距離”で判断します。
■ 注意点①:養子の取り扱い
養子も法定相続人に含まれますが、相続税法上の控除計算では人数に制限があります。
-
実子がいる場合 → 養子1人までカウント可能
-
実子がいない場合 → 養子2人までカウント可能
つまり、実子が3人いる上で養子を5人迎えた場合、「控除が爆増するのでは?」という期待は無効です。
■ 注意点②:相続放棄と法定相続人の数
相続放棄をした場合でも、基礎控除の計算上は法定相続人にカウントされます。
例)配偶者+子3人のうち、1人が放棄
→ 法定相続人は「4人」として基礎控除を計算(3,000万+600万×4=5,400万)
「放棄したから関係ないでしょ?」と思っていても、税務の世界では“存在していた事実”が重要です。
■ 注意点③:法定相続人がいない場合
法定相続人がいない場合、遺言書がなければ最終的には国庫に帰属することになります。
また、基礎控除額も最小の「3,000万円」に固定されるため、相続税の負担が重くなるケースも。
「自分には相続してくれる人がいないから大丈夫」と思っていると、思わぬ税負担を残してしまうこともあるので、生前に遺言や遺贈の検討をしておくと安心です。
■ まとめ|相続税の出発点は「法定相続人の確認」から
法定相続人の確定は、相続税申告の第一歩であり、基礎控除・税率・非課税枠など、すべての基準になる重要な情報です。
-
民法上の定義を正しく理解する
-
養子の人数制限に注意
-
相続放棄でもカウント対象になる
-
曖昧な関係性(内縁など)は含まれない
これらのポイントを踏まえたうえで、早めに相続の準備・見直しを行うことが、円滑な手続きと節税への近道になります。
当事務所では、相続税申告のサポートはもちろん、生前対策や法定相続人の確認支援なども含めて、丁寧にご案内しています。
戸籍の取り寄せから複雑な家族構成の分析まで、“家系図と税額の見える化”をお手伝いします。