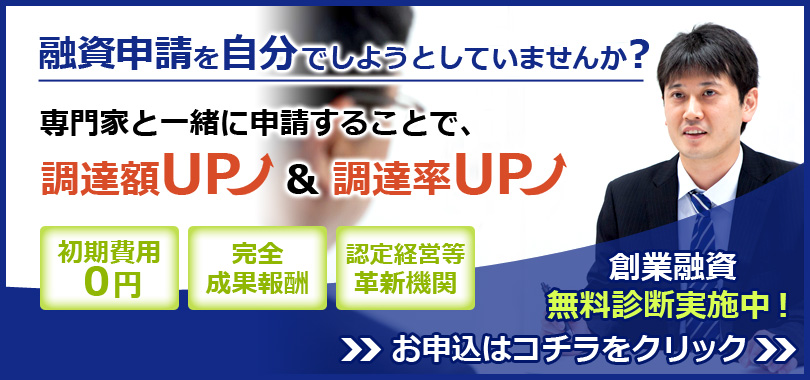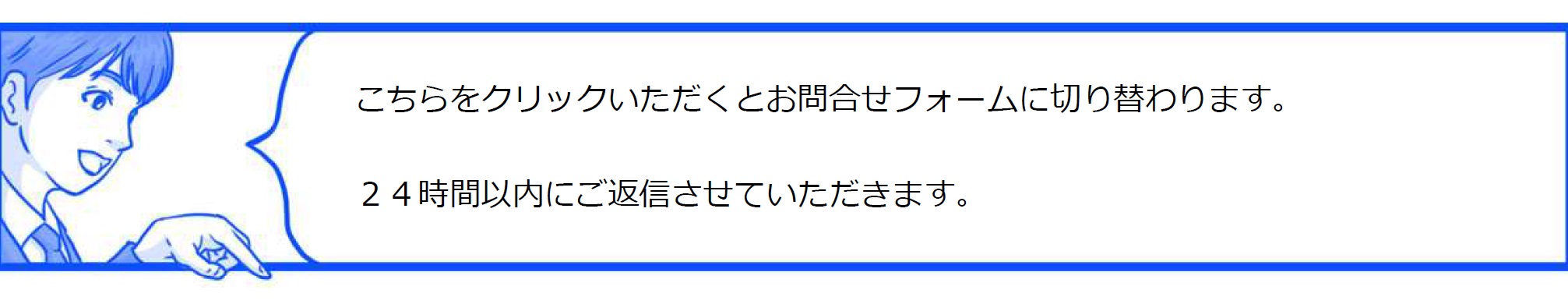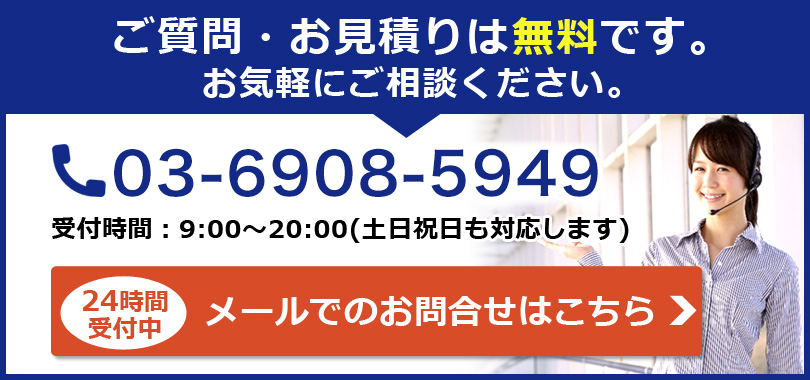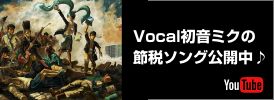税理士ブログ
【インボイス制度の注意点|事業を始めたばかりの方へ】
2023年10月から、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が始まりました。これは、消費税の仕入税額控除を行うために「インボイス(適格請求書)」を発行・保存することが必要になる制度です。
すでに取引先から「インボイスを発行できますか?」と聞かれたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、開業して間もない事業者の方に向けて、インボイス制度で注意すべきポイントをわかりやすくご説明します。
1.インボイス発行事業者になるべきかどうか
開業直後は「免税事業者」として、一定期間、消費税の納税義務が免除されています。しかし、免税事業者のままだと、取引先が仕入税額控除を受けられなくなってしまうため、「インボイスを発行してほしい」と求められる場面があります。
その場合、税務署に「インボイス発行事業者」の登録申請をする必要があります。登録すると、消費税の申告・納税が必要になるため、売上や経費の管理、会計処理の手間も増える点に注意が必要です。
「今すぐ登録すべきかどうか」は、事業の状況や取引先との関係を踏まえて慎重に判断しましょう。
2.請求書に記載すべき内容が増える
インボイス制度では、**取引先に交付する請求書に一定の記載事項が求められます。**たとえば、次のような項目です。
-
自社の名称と「登録番号」
-
取引年月日
-
商品やサービスの内容(できるだけ具体的に)
-
金額(税率ごとの区分が必要)
-
消費税額または税込金額
-
相手先の名称(一定の場合)
これまで使用していた請求書フォーマットでは記載内容が不足している可能性があるため、テンプレートの見直しや請求書ソフトのアップデートを行う必要があります。
3.免税事業者のままでは不利になることも
免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先が消費税の控除を受けられなくなります。
その結果、取引先が「インボイスを発行できる他社に切り替える」といったケースもあり得ます。
特に、法人や大手事業者と取引を行っている、または行う予定がある場合は、インボイス対応が取引継続の条件になることもあるため、早めの検討が必要です。
4.帳簿や会計処理も見直しを
インボイス制度では、売上や経費の消費税率ごとの管理が必要になります。
また、帳簿や領収書・請求書の保存ルールも厳しくなるため、対応している会計ソフトを導入する、税理士に相談するなどの対応をおすすめします。
5.経過措置の活用も検討を
制度開始から6年間は、「経過措置」として、インボイスがない取引であっても、一定割合の仕入税額控除が認められています(例:2023年度は80%控除)。
ただし、この措置は年々縮小され、最終的にはインボイスがないと控除できなくなるため、長期的な視点で対応を考えておくことが大切です。
おわりに
インボイス制度は、事業規模や業種にかかわらず影響がある制度です。特に開業して間もない方は、「登録すべきかどうか」「請求書の書き方はどうするか」など、迷う場面も多いと思います。
当事務所では、お一人おひとりの状況に合わせたアドバイスを行っております。
不安な点や不明な点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。