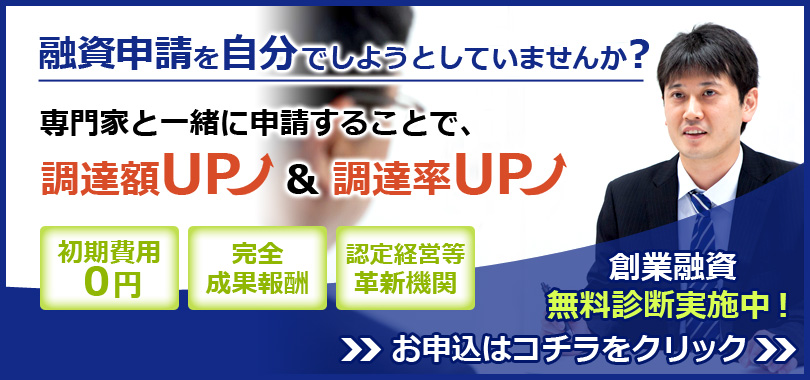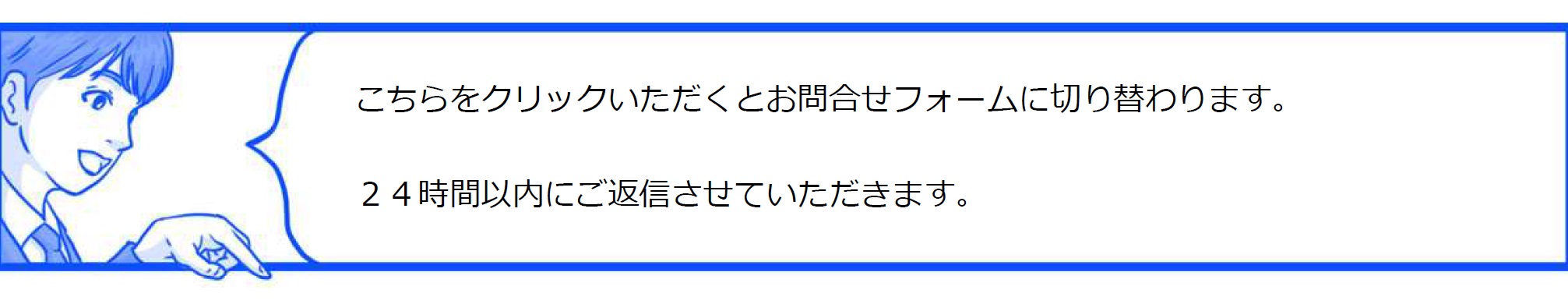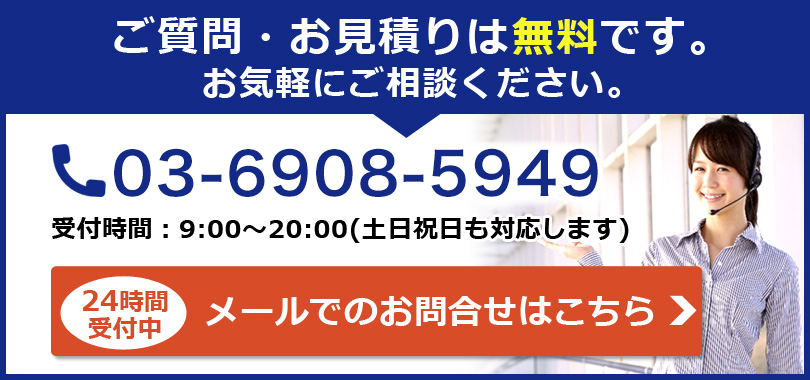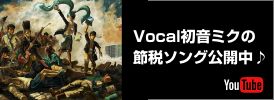税理士ブログ
会社の福利厚生、どこまでOK?|税務上の取り扱いと注意点
こんにちは、新宿区西新宿の税理士法人阿部会計事務所の税理士阿部です。
従業員のモチベーション向上、離職防止、企業イメージアップ。
福利厚生制度は、企業にとって“人材投資”の重要な柱のひとつです。
しかし、この制度、税務の世界では「使い方を間違えると課税対象になる」というややこしい一面もあります。
この記事では、会社の税務上の福利厚生の基本的な考え方と、注意すべきポイントを分かりやすくお伝えします。
■ 福利厚生費とは?その定義と目的
福利厚生費とは、従業員の生活の安定や職場環境の改善を目的として、会社が支出する費用です。
例えば以下のようなものが該当します:
-
健康診断の費用
-
慶弔見舞金
-
社員旅行・社内イベント
-
食事補助・社食・弁当代の補助
-
スポーツジムの法人契約
-
保養所・レクリエーション施設の利用
これらは正しく実施すれば「福利厚生費」として会社の経費にでき、かつ従業員の給与課税の対象とならない、つまり両得の制度です。
ただし、“正しく実施すれば”です。自由すぎる運用は思わぬ税務リスクを招きます。
■ 福利厚生が「給与」とみなされるケース
次のようなケースは、福利厚生と認められず「給与」として従業員に課税される恐れがあります。
-
社員の一部だけが対象(社長と専務しか旅行していない、など)
-
家族同伴の社員旅行(しかも会社負担)
-
高額な支給で実質“給料の上乗せ”状態
-
社外の個人(友人や取引先など)も参加
-
社員の個人的趣味に近すぎる費用(ゴルフ合宿とか)
「社員旅行です!」と言い張っても、実態が“社長の趣味合宿”だった場合は認められません。
■ よくある福利厚生制度と税務上のポイント
① 社員旅行
・4泊5日以内の国内旅行であれば、会社負担でも原則課税されません(要件あり)。
・参加者が全体の50%以上であることが条件。
・旅費や宿泊費はOKですが、お土産代や個人的な観光費用はNG。
② 食事の補助
・社員食堂を設置していたり、仕出し弁当を補助していたりする場合、一定の自己負担があれば課税されません。
・「全額会社持ち・高級弁当毎日支給」となると、給与と判断されることも。
③ 慶弔見舞金
・結婚祝金、出産祝金、香典などは、社会通念上相当な金額であれば課税されません。
・あくまで「一律の基準」であることが重要で、社員によって金額を変えると課税リスクが高まります。
■ 福利厚生制度を導入する際の注意点
-
全社員が対象であること
→ 一部の役員や管理職のみを対象とした制度は「給与課税」となる可能性が高くなります。 -
社会通念上相当といえる内容か
→ 一般的な水準を逸脱した豪華すぎる内容(年3回の海外旅行、毎月の高級ワイン支給など)はNG。 -
記録と根拠を残しておく
→ 実施した行事の案内、参加者リスト、領収書などの保存は必須。調査時に「実態がない福利厚生」は否認されます。
■ 福利厚生費が有効な理由
福利厚生制度は、適切に整備すれば:
-
企業の魅力向上(採用・定着に寄与)
-
従業員の士気向上・満足度アップ
-
経費としての処理(節税)
-
給与課税を回避できる
といった効果が期待できます。
ただし、制度設計を誤ると「給与課税+源泉徴収義務違反」などの指摘が入る可能性もあるため、導入時・見直し時には税理士等専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
■ まとめ|“社員想い”と“税務リスク”は紙一重
福利厚生制度は、会社の文化をつくる大切な施策ですが、税務上のルールを外れると「想いやりが過ぎて課税対象に」なる落とし穴があります。
節税目的だけでなく、本来の「社員のため」という目的を忘れずに、公平・妥当・継続的な制度設計を心がけましょう。
当事務所では、福利厚生制度の設計支援から税務的リスクの洗い出し、実務上の運用アドバイスまで幅広く対応しております。